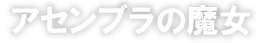Ubuntu(ウブントゥ)はLinuxディストリビューションの一つで、GNU/LinuxベースのOSです。それ以前の他のディストリビューションに比べると、インストールが容易で(戸惑うことが少なく)、デザインもかなり洗練されています。
インストールスキャナを使ってみる
Windowsの共有フォルダをマウント
Ubuntu Japanese Team
いきなりマシンをUbuntu専用としてしまうことはリスクもありますので、まず仮想ハードディスクイメージを使って見ることにしました。 何年か前は、仮想ハードディスクイメージはVMWare上で走るように作られていましたが、最近はVMWareではなくVirtualBoxで走るようになっています。
Ubuntu Japanese Teamのダウンロードのページの"VirtualBoxでの利用方法"の説明にあるように、VirtualBoxをダウンロード、解凍してインストールします。特に戸惑う様なところはありません。ダウンロードからインストールまで20分程度で完了すると思います。
Ubuntu Japanese TeamのダウンロードのページからUbuntu日本語Remixの仮想ハードディスクイメージをダウンロードします。torrentファイルもダウンロードできますが、Bittorrentを使わくても数15分程度でダウンロードできます。ダウンロードされた仮想ハードディスクイメージは圧縮(ZIP)されていますので解凍し、適当なディレクトリに置きます。
VirtualBoxを起動して回答した仮想ハードディスクイメージが起動できるようにします。VirtualBoxの新規ボタンを押すと、「仮想マシンの作成」ダイアログが開ます。ここで、名前、タイプ、バージョンを設定します。名前は適当で良いと思いますが、"Ubuntu"と入力するとタイプが自動的に"Linux"に設定されます。タイプはLinux、バージョンはUbuntuに設定します。
「次へ」を押すとメモリサイズの設定画面が開きます。ここでは少なくとも512MB以上のメモリを確保する必要があります。 その次はハードドライブの設定です。ここで、「すでにある仮想ドライブファイルを使用する」を選択して、さきほど解凍した仮想ハードディスクイメージを指定します。「作成」を押すと仮想マシンが作成され、「起動」ボタンを押すと、ここで作成した仮想マシン(仮想ハードディスクイメージ)が起動します。
仮想マシンの設定は他にも多くの項目がありますが、後から変更することができます。(数年前の)VMWareに比べると設定がわかりやすく変更も容易だと思います。
仮想マシンが起動してUbuntuが(最初に)起動すると、キーボードやタイムゾーン等の設定が求められます。必要な操作はすぐに終わりますが、その後セットアップが完了するまで20分程度の時間がかかります。
ネットワークの確認も兼ねて("Ubuntuの設定"の段階ではネットワークに関して何も設定していません)Firefoxを起動すると、問題なくネットに接続できています。一応、インストールは成功したようです。
ここ1、2年新しくLinuxをインストールしたことはありませんので他のディストリビューションも進化していると思いますが、Ubuntuはインストールに迷う点が少なく(設定項目も少ない)非常にたやすくインストールできたと思います。
Ubuntsuでスキャナが使えるか試してみました。
Ubuntuをインストールするとデフォルトで「Sinple Scan」というソフトがインストールされます。これはプレビューの機能が無いらしく、全領域を一気にスキャンします。保存の前に「切り抜き」」の機能で領域を選択できるのですが、その時に表示される画像は小さいのでござが大きく、正確に切り抜こうとすると全領域を一旦保存して、GIMP等を使って切り抜いた方が良いと思います。またスキャンパラメータの設定も無く、ホワイトバランスも多少ずれたりしていますのでそれも後から補正する必要があるかも知れません。Windows上で走る純正のスキャンソフトに比べると、効率が悪いようです。
GIMPでもスキャンできるはずなので、GIMPをインストールしてみたのですが、「"flegita-gimp"プラグインがクラッシュしました」のエラーが発生。GIMPでのスキャンは断念しました。
これまでGIMPにスキャンのメニューがあることは知っていましたが、使ったことはありませんでした。スキャナはCanonのLiDE 210で純正ソフト MP Navigator EXを使ってスキャンしてそれを一旦保存、GIMPで編集していました。Windows上のGIMPで直接スキャンしたらどうなるのか?試してみました。
GIMPの「ファイル」-「画像の生成」-「スキャナとカメラ」を選択すると、「ソースの選択」ダイアログが表示されますので、ここで「CanoScan LiDE 210 170(32-32)」を選択すると、純正のドライバー(MP Navigator EXから起動されるものと同じです)が起動しますので、詳細なスキャンパラメータはこれまでどおり設定出来ますし、操作性もこれまでと同じです。そしてスキャンが完了すると、画像はGIMPに直接転送されます。これまでは、一旦ファイルの保存(これが結構遅いです)してGIMPで読みこんで編集していましたので、この方法に変更することで作業時間を短縮できると思います。思ったよりこれは便利です。Ubuntuでスキャンという目的は達せられませんでしたが、この発見は収穫でした。
昔(10年以上前)はSambaの設定が複雑でインストールしただけではすぐに使えないことが多く、結構苦労しましたが、最近はほとんど戸惑うことなく使えるようになったと感じていましたが、今回は少し戸惑いました。Ubuntuをインストールした直後の状態で、ファイルブラウザ(Nautilus)で「ネットワーク」-「Windowsネットワーク」を開くと、「場所をマウントできません サーバーから共有リストを取得出来ませんでした」というエラーが表示されます。デフォルトでSambaがインストールされていないようなので、sambaをインストールすると上記のエラーは解消されましたが、Nautilusの「ネットワーク」-「Windowsネットワーク」にはWindowsの共有フォルダは現れません。Windows側でワークグループを設定していたので、sudo system-config-samba でワークグループを設定しましたが状況は改善されません。/etc/samba/smb.confの修正が必要との情報もあり、globalセクションに以下の2行を追加しましたが、状況は変わりません。
[global] client lanman auth = yes client ntlmv2 auth = no
以前はどこかに「サーバーに接続」みたいなメニューがあって、そこからサーバーに接続したような記憶があったのですが、それが見当たりません。しばらく、ネットで調べてメニューがグローバルメニューとして(nautilusのウィンドウ内ではなく)デスクトップの上側に(以前のMacOSみたいな感じです)表示されることにやっと気づきました。しかも、そのメニューはカーソルをそこに移動しなければ表示されないので、予備知識がなければ非常にわかりにくいです。設定によってはnautilusのウィンドウ内に表示することもできるようですが、これで結構時間を浪費しました。 「ファイル」-「サーバーへ接続」より、以下を入力してやっとWindowsの共有フォルダに接続することができました(Nautilusの「ネットーワーク」-Windowsネットワーク」以下にWindowsの共有フォルダが表示されました)。
サーバー名:129.168.1.2←WindowsサーバーのIPアドレス 種類:Windows共有 フォルダ:htdocs←Windowsマシン上の共有名
以前Nautilusにはアドレスバー(ロケーションバー)が表示されていたような記憶がありますが、今回のインストールではアドレスバーは表示されず、これを表示する方法を探すのにも時間がかかりました。設定で表示できるようにできるようですが、とりあえず今回はCtrl+Lで一時的に表示することで対応しました。
これでUbuntuからWindows上にあるHTML生成のためのソースにアクセスできるようになったので、早速HTML生成の実験と行おうとしたのですが、Nautilusの接続はファイルシステムにマウントされるわけではないらしく、シェル上から共有ファイルにアクセスできません。
代わりにsmbfsを使ってマウントすることにしました。smbfsはデフォルトではインストールされていないようでしたので sudo apt-get install smbfs でインストールしました。マウント先のディレクト /mnt/htdocsを作って、sudo mount -t smbfs //192.168.1.2/htdocs /mnt/htdocs/ -o username=name でマウントすることが出来ました(//192.168.1.2/htdocsはWindowsマシンのIPアドレスと共有フォルダ名、/mnt/htdocsはUbuntu側にあるマウント先ディレクトリ(ここにマウントされます)、nameはWindowsマシン上のユーザー名)。